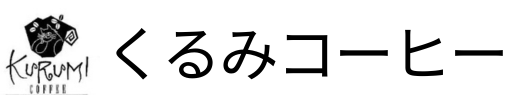父のことを書くのは、きっと山桜に騙されているから。
去年の6月、父の胆嚢炎の手術のため東京の病院にいた。
手術の付き添いのためだ。
手術室の前のソファーに座り、一人中庭を見ていた。
綺麗に刈り揃えられた庭木の中、何本かの雑草がひょいと立ち上がり、
その雑草に夏草の蔓が巻き付きはじめていた。
空は浅く、青白く、病院の建物の先の大きな木々が風に少し揺れ、
ところどころに見える終わりかけのツツジの花は赤茶色にうな垂れていた。
手術室の前の白い廊下は、窓越しの陽射しを受けながらも冷たく、
隣の部屋の殺菌室に足早にトレーを持って来ては帰る看護師の
足音だけが目立った。
廊下を曲がった向こう側の通路は患者や関係者でごった返しているのに
ここは、まるで別世界だ。
病院のスタッフは無駄な動きなどしません、というようにスマートできっと的確で
洗練されている。
「これが、東京の総合病院かあ」
ここで働く人たちは、何となく機械に似ている。
腰に消毒液を付けたピンク色の看護婦さんも、
チェックのベストを着た事務の女性も、phs で話しながら歩く医者たちも。
いったい、この人たちに帰るところはあるのだろうか?
もしかして、こうして、ここで永遠に働き続けているのだろうか。
ずーっと昔から、そして、これからもずーっと。
父のことを想い出していた。
私の父は学歴がないので、母は私に教育をと思った。
けれど、私は勉強が好きではなかった。母は頭の良い人だったが、
私は父親似と言われて育った。
父は婿ではないが、母の親戚の敷地で過ごした。
小さい頃キャッチボールをしたり、釣りに連れて行ってもらったりしたが、
母はそういうことが嫌いだった。
だから私も悪い事だとずっと思っていた。
年に何度か電車で映画を観に行くのを楽しみにしていた。
帰りに映画館の近くの食堂に寄ってラーメンを食べて帰って来るのが楽しみだった。
映画館までの坂道を親子三人で手をつないで歩いた。
私の半ズボンが下がると、父がそのたび止まって、しゃがんでは私のズボンを上げてくれた。
へその上まで上げるので、パンツが食い込んで痛かった。
穏やかで優しく怒ったことのない父だった。
母は「優しい人は誰にだって優しいんだ」と毒づいていた。
ある日、父は家を出て行った。
「じゃあ、行ってくっから」が最後の言葉だった。
専業主婦だった母はスーパーの惣菜部にパートで働き始めた。
父からの収入は途絶えた。
父は女と暮らしていた。
手術室の前の白い廊下の空気は異様に乾いて喉がえづいた。
父とは一緒に住んでいたより、離れて暮らした方がはるかに長い。
母には内緒で病院に来ている。父は「ありがとうね。悪いね」と何度も繰り返していた。
手術が終わり、酸素マスクを付けてナースステーションのそばの部屋にいる。
眠っている父は昔と変わらず、穏やかで優しげに見えた。
病院を出ることができなかった。
全身の力が抜けて、白い廊下のソファーの上で、大きく足を延ばし
うな垂れたツツジをしばらく見ていた。