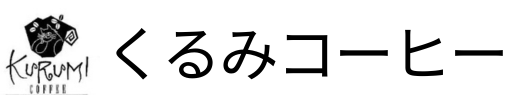新しい年が明けました。
皆様にとって素晴らしい1年になりますように。
今年も、心を込めて焙煎致します。
コーヒー豆の焙煎を仕事にしてから
今年で11年目。
店を構えて9年目になります。
昨年は店舗の移転もありました。
年頭に当たって
改めてコーヒーの話をしたいと思います。
少し長い話になりますが、お付き合いください。
コーヒーの木は
エチオピア高原に広がる多雨林の灌木に発生しました。
葉は常緑で
光沢のある細長い円い実を付けます。
世界の貿易額の中では、石油につぎ金銭的価値が高く
2,500万人以上の人が
いろいろな形で関わり生計を立てています。
(コーヒー生産量は、年間1億2,800万袋。 ※1袋60㌔ 2006/2007年)
コーヒーの栽培は
赤道を上下に25度の範囲の「コーヒーベルト」と呼ばれる
熱帯、及び亜熱帯地方で行われています。
気温21°c〜27°c
年間降水量1,500〜2,000ミリ
標高1,000m以上の高地が適しています。
世界で約60カ国で栽培されています。
苗木を作り発芽、植樹、剪定を経て、
約3年でジャスミンの香りを漂わせながら白い花が咲きます。
この花は2、3日で散り、
それから円い緑の実が付き、
約7ヶ月でその実が完熟して赤くなり、
収穫の時期を迎えます。
赤い実の果肉を取って水洗い、乾燥させ
表面の薄い皮を取って生豆の出来上がりです。
ひじょうにデリケートな作業を、
広大な敷地で手作業で行われることの多い作物です。
このように多くの労力を要する作業に比べて、
人々の一日の平均収入は3ドルにすぎません。
不幸だとは言えませんが、
彼ら彼女らのほとんどが、医療はもちろん
教育も上下水道も電気さえ届かない
赤貧の暮らしをしています。
コーヒーの最も古い記録は
西暦900年頃
ペルシャの医師ラーゼルによって煮出した汁を患者に飲ませたところ
「胃が良くなり、覚醒、利尿の効果あり」という記述があります。
6世紀には羊飼いのカルディが
木の実を拾って食べた羊が踊るように元気になったのを見た話。
13世紀にはイエメンのモカで
山中に追放されたイスラム僧シェイク・オマールが
鳥の食べた実を病人に与えたところ病気が治った話などがあります。
13世紀頃までは
コーヒーはイスラム教の寺院のみで飲まれていたようです。
焙煎が行われるようになったのは13世紀中頃、
そこから各地に広がって行きます。
1554年イスタンブールで
コーヒーハウス「ハーネス」オープン、アラブ、トルコ地方に定着していきます。
1615年イタリアへ
1640年以降イギリス、フランス、オランダ、ドイツ、オーストリアとヨーロッパ地方へも拡がりました。
また、15世紀のヨーロッパは
マルコポーロの東方見聞録以来、アジアへの関心が高まり
大航海時代へと入ります。
キリスト教の普及とアジアへの航路の拡大が、
植民地支配への歴史と重なります。
重工業が発展し、それに伴い武力が強化され
ヨーロッパからアフリカへは武器や重機が輸出され、
アフリカからアメリカへは奴隷、
アメリカからタバコや砂糖、綿花が奴隷によって作られヨーロッパへ入ります。
アフリカからヨーロッパへは金や象牙、
またインドや東南アジアからは香辛料や紅茶が送られました。
コーヒーは世界的に流通し始めましたが、
この時点では苗木の流通は行われていませんでした。
イスラムの商人がイスラム教の寺院内だけで栽培して
苗木の持ち出しを固く禁じていたのです。
しかし1695年、インド人のババ・ブータンがメッカの巡礼に来た際、
密かに持ち帰り、これを南インドで栽培。
成功したその苗を1699年インドネシアへ移植。
1706年インドネシアからアムステルダムの植物園へと移動。
そこからフランスへ渡り、
西・東インド会社によって西インド諸島や中南米へと拡がって行きます。
日本へは1641年、
鎖国中の出島へオランダ人が持ち込んだのが最初とありますが、
たぶんその前に南蛮船によって、
室町時代の末期には堺港あたりに入っていたのではないかと予測されます。
このようにして、コーヒーは全世界へと拡がっていったのです。
近代のコーヒー産業はアメリカの開拓史と共に発展します。
1773年のボストン茶会事件(※イギリス本国の茶条例により紅茶に過度な税を掛けたため、
怒った現地人は、ボストン港に茶箱を投げ捨て、アメリカ人はコーヒーを飲む、と宣言した)
その後、独立戦争、南北戦争を経て拍車のかかった近代化は、
コーヒー産業の繁栄へと繋がっていくのです。
鉄道や電話、蒸気船など交通、通信網の発展、
新聞や雑誌など宣伝活動の拡大によって
20世紀初頭までには、コーヒーは全世界規模の消費物資となっていきました。
それと共にコーヒーには大規模な需要があるため、
実業家たちはコーヒー市場の独占を企てます。
ブラジルに大規模な農園を作り、その結果、
価格の下落を招いて
市場の高騰と暴落のサイクルが生まれました。
コーヒーの近代史は産業の発展と技術の革新に大きく関わっています。
それだけ経済を回せる大規模な消費物資となったのです。
しかし、その結果、
産地では原住民が土地を奪われ、弾圧され、
農地拡大のため自然が破壊され、環境の悪化を招きました。
そんな状況が続くなか、アメリカはベトナム戦争(1965〜1975)へと突入して行きます。
ベトナム戦争下、反戦運動が高まります。
そして新しいコーヒーハウスも誕生していきます。
時代は中流階級の若者たち中心に
対抗文化(カウンターカルチャー)が台頭していくのです。
ボブ・ディランやジャニス・ジョップリンの時代です。
東洋思想や先住民への回帰を志した「ヒッピー」や
民主社会のための学生組織を目指した「イッピー」たちが
政治、哲学、風俗の渾然一体となった「ポップカルチャー」を作っていきます。
そんな若者たちがコーヒーハウスに集まるようになり、
コーヒーもまたポップカルチャーの波に飲まれていったのです。
1966〜1967 バークレイのパインストリートに「ピーツ・コーヒー&ティ」がオープンします。
この店を作ったアルフレッド・ピートは
今までのアメリカのコーヒーの概念にはない、「産地によって味が違う」ことが分かっていたのです。
そして、焙煎の方法やブレンドにも高度な知識を持っていました。
そのピートに影響を受けた三人が
1971年最初のスターバックスコーヒーを開業したのです。
その後スターバックスコーヒーは、
エスプレッソに影響を受けて1983年位から現在の形に移行していきます。
アレンジコーヒーの時代です。
そして2000年を過ぎ、コーヒーは
より高品質を求めるようになってきました。
流通経路を明確にし、豆の品質や香味を重視しました。
どの農園のどの品種の豆をどんな方法で作るか、ということに
重点を置くようになってきたのです。
また土壌を改良し
自然に配慮したオーガニックやバード・フレンドリー、
レイン・フォレストなどの動きも盛んになっています。
そして現在のサード・ウエーブへと繋がっているのです。
コーヒーには
力の強い者が弱い者から搾取するという不公平の歴史がありました。
何百年も続いた
このシステムを変えることは簡単なことではないでしょう。
大きく経済が回れば
格差が大きく生じるのも必然のことです。
しかし
競争の市場だけではない、多様性のある対応の仕方を
切に望んで仕方がないのです。
今、コーヒーの需要を喚起するテレビや新聞、雑誌に
何とも落ち着きのない違和感を持ってしまうのは、
何故なのでしょうか?
コーヒーは
エチオピア高原の灌木から生まれた、名もないアカネ科の植物でした。
その植物が世界を動かし今もどこかの国では、
泣いたり、笑ったり、汗を流したり、血を流したりしているのでしょう。

そして 、八郷の丘の上では
「一杯のおいしいコーヒーのため」小さな焙煎器を回して
少しずつコーヒーを淹れているのです。