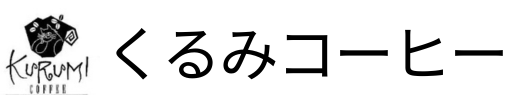その犬は16歳と8ヶ月で逝った。苦しい最期だった。
背中の皮が剥け、痛さに苦しみ、犬小屋と垣根の間の狭い隙間に鼻先を入れて、夜じゅう鳴いていた。
朝には、力尽きて横になった。でも激痛は睡りを許さなかった。
視力のない真っ黒な瞳から大きな涙がこぼれた。
全身から生臭い匂いを発して時々切ない悲鳴をあげた。
そして日が傾き、たくさんの小虫が飛び交う頃この世を去った。
西の空は淫靡な夕焼けで羊飼いの星が光っていた。
その犬はおよそ番犬にはならないが、誰からも好かれる犬だった。
穏やかで怒った姿を見たことがなかった。
鳥が自分のエサを食べに来ても、猫が犬小屋に入って寝ていても黙って見ていた。
猫が大好きで猫を見ると「クーン、クーウン」と呼んでいた。
その犬が亡くなったその日は猫も落ち着きがなかった。
二階の屋根から飛び降りてみたり、犬小屋の近くの水道の蛇口にパンチしてみたり、
わけもなく二匹の猫でケンカしてみたり。
猫をつかまえて腹をさすってみると、柔らかい毛の下で心臓が激しく波打っていた。
アブに刺されながら、三年半前に亡くなった姉犬のそばに犬を埋めた。
「小さい頃みたいに、また二匹で駆けまわって遊びな」
いい子だな、いい子だな、何度も頭を撫でてやった。
薄闇は頭の中まで染みてきて、あたりは朧げになった。
「薄闇の空に小虫(ティンカーベル)の飛ぶような童話(おとぎ話)か二十六夜月」
ハナ、さようなら、いい子だ、いい子だ。
ハナ、さようなら、いい子だ、いい子だ。